はじめに
AmazonギフトカードやAppleギフトカード、Google Playカードなどのデジタルギフトカードは、受け取る側に税務上の落とし穴が潜んでいることをご存じでしょうか?
- 「副業で受け取ったAmazonギフト券、確定申告が必要?」
- 「懸賞で当たったAppleギフトカード、税金は?」
- 「複数回に分けて受け取ると贈与税対象になるの?」
知らないと重大な税務トラブルに発展する可能性があります。本記事では贈与税・所得税・一時所得の制度と課税の仕組みを図表や計算も交えて、解説します。
ギフトカードを「もらう」時に必要な税務知識

デジタルギフトカードは一見、現物支給のように見えます。しかし、税務上では金銭と同様の価値を持つ資産として認識され、取得経路によって異なる税制が適用されます。
ギフトカードにかかる税金は、以下の3つのケースによって異なります。
取得方法と具体的な税務区分を、国税庁の定義に沿って解説します。
| ケース | 税務区分 | 非課税限度額 | 課税対象 |
|---|---|---|---|
| 家族・知人からの贈り物 | 贈与税 | 年間110万円 | 超過分に贈与税が課される |
| 企業・クライアントからの報酬 | 所得税 | 年間20万円(副収入) | 所得税の課税対象、確定申告が必要 |
| 懸賞・抽選・キャンペーン当選 | 一時所得 | 年間50万円 | 超過分の半分が課税対象(×½) |
【贈与】家族や知人からギフトカードを受け取った場合
誕生日やお祝い事などでデジタルギフトカードを贈られるケースの場合、「贈与」として扱われ、贈与税の課税対象になります。
🔸 非課税限度額:年間110万円まで
国税庁によると、1月1日から12月31日までの間に、複数の贈与者からの総額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。逆に、少額でも年間合計が110万円を超えた時点で、贈与税の申告が必要です。
🔸 注意点:贈与者が複数でも合算される
例えば、Aさんから50万円、Bさんから80万円のギフトカードを受け取った場合、合計130万円となるため、110万円を超える20万円分に贈与税が課税されます。
🔸 相続時精算課税制度を選ぶとどうなる?
贈与者が親や祖父母であれば、「相続時精算課税制度」の選択肢もあります。生涯2,500万円までの贈与に贈与税がかからず、最終的に相続のときに合算されて課税されます。
【報酬】企業からギフトカードを受け取った場合
フリーランス、副業、アフィリエイトなどで、報酬としてギフトカードを受け取る場合、現金報酬と同じく「所得税」が課税されます。
アフィリエイト収入をAmazonギフト券で受け取った
ポイントサイトの報酬をギフト券で受け取った
アンケート謝礼としてGoogle Playカードを受け取った
会社員でも副収入が年間20万円を超えると確定申告が必要です。ギフトカードが報酬である限り、「受け取った金額=収入」とみなされます。ギフト券の額面を円換算して計上する必要があります。
【懸賞】キャンペーン・抽選・プレゼント当選の場合
懸賞や抽選、キャンペーンなどでギフトカードをもらった場合、一時所得として税務上処理されます。
🔸 一時所得の課税計算式
(ギフトカードの価値 − 特別控除50万円)× 1/2 = 課税対象額
たとえば、懸賞で10万円のAppleギフトカードを受け取った場合、 50万円の控除内に収まるため、税金はかかりません。しかし、複数回の当選などにより年間で60万円分の一時所得を得た場合、 (60万円 − 50万円)× 1/2 = 5万円が課税対象となります。
所得区分の間違いが招く税務調査のリスク
SNSインフルエンサーが報酬としてギフトカードを受け取ることは珍しくなく、未申告で数十万円相当のギフトカードを受け取っていたら、税務調査・追徴課税を受ける可能性もあります。
したがって、高額なギフトカードを受け取った人は「贈与」「報酬」「懸賞」なのかを把握し、それに応じた申告・納税が求められます。特に高額になる場合は、税理士への相談をおすすめします。
贈与税がかからない金額は?|年間110万円の枠を超えるとどうなる

日本の贈与税制度では、1月1日~12月31日の1年間における贈与額の総額から、以下の控除枠が自動的に差し引かれます。
- 暦年贈与:年間110万円の基礎控除(国税庁)(マネジー)
つまり、相手から贈与された財産の合計が110万円以下であれば、税務署への申告は不要です。一方、110万円を超えた分には贈与税がかかり、贈与税申告書の提出が必要です。
複数回のギフトカードもまとめて計算される
贈与は一回単位ではなく、「1年単位の累計額」で判断されます。
- 友人A:50万円+友人B:70万円=合計120万円→110万円の控除を超える10万円に贈与税がかかる
(贈与税は累進的でケースにより税率が変わります(マネジー)
多数回の分割受領でも、年末に累計すると贈与税の対象になる可能性があります。
相続時精算課税制度とは?
通常の暦年贈与とは異なる「相続時精算課税制度」は、以下の条件を満たす場合に利用できます(国税庁)
- 贈与者が60歳以上の親・祖父母
- 受贈者が20歳以上の子・孫
- 申告の際に「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要
→贈与税の基礎控除:累計2,500万円+年間110万円枠
→2,500万円超部分には一律20%の贈与税が課され、相続時に過去贈与分も含めて相続税が精算される(セゾンのくらし大研究)
| 項目 | 暦年贈与 | 相続時精算課税制度 |
|---|---|---|
| 非課税限度 | 110万円/年 | 110万円/年 + 累計2,500万円 |
| 税率 | 累進課税(10~50%程度) | 一律20%(超過部分) |
| 将来の相続影響 | なし | 相続計算に加算され、相続税と精算 |
| 制度変更 | いつでも可能 | 一度選ぶと暦年課税に戻せない |
相続トータルでの節税を考える場合、遺産移転を予定しているなら有効な選択肢となります。
贈与税の税率と計算方法
贈与税の税率は高額贈与ほど高率になります。以下は2025年時点の目安です(国税庁より)。
| 課税価格(基礎控除後) | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| ~6,000万円 | 30% | 205万円 |
| 6,000万円超~ | 45% | 805万円 |
- 例:課税価格:500万円の場合 → 30%×500万円 - 205万円 = 95万円が納税額
控除枠を超えた場合の対応
ケースA:一人から120万円の贈与を受けた
→基礎控除110万円を差し引き、10万円が課税対象。税率10%で、贈与税=1万円。
ケースB:年間に複数人・何回も受け取った合計250万円
→110万円控除後:140万円課税対象 →30%×140万円-25万円=17万円の納税。
こんな贈与は非課税?社会通念や例外への注意
以下は贈与税の対象外または非課税扱いになるため、申告不要です。
- 香典、結婚祝い・お年玉など社会通念上相当な金銭(香典・慶弔など)
- 商品券・プリペイドカードの購入自体(消費税上は非課税だが、贈与税上の扱いは別)(国税庁)
ただし、「高額の結婚祝いギフトカード」は非課税対象外となる可能性もあるため、社会通念の範囲か超えるかで分かれる点に注意してください。
✅ まとめ:第2章のポイント
- 暦年贈与の基礎控除は110万円―超えた分に贈与税が課される
- 分割や複数人から受け取っても、合算して課税判断される
- 親・祖父母からのまとまった贈与には、相続時精算課税制度(特例基礎控除:累計2,500万円)が有効
- 贈与税率は累進的で対象金額が大きいほど負担増
- 香典や祝儀などは社会通念上非課税
報酬としてギフトカードを受け取る場合の所得税

企業やクライアントから、業務の対価としてギフトカード(例:Amazonギフトカード、Google Playギフトカードなど)を受け取る場合、現金報酬と同じく「所得」とみなされるのが税務上の基本ルールです。そのため、所得税の課税対象として取り扱う必要があります。
- 個人事業主が仕事の対価として受け取ったギフトカード → 「事業所得」または「雑所得」
- アフィリエイトやポイントサイト報酬 → 「雑所得」または「事業所得」
国税庁でも「現物支給」で受けた報酬は給与所得または雑所得・事業所得に該当し、所得税課税の対象になると明記されています(国税庁)
副業・報酬:20万円ルールと確定申告
会社員が副業でギフトカード報酬を受け取る場合、所得の合計額(収入-経費)が年間20万円を超えると、確定申告が必要になります。これは国税庁および税務専門家も一様に指摘している基準です。
また、課税所得が少額でも、住民税の申告は収入があれば必要です。
確定申告での正しい記載方法は以下の通りです。
- 収入金額:ギフトカードの額面を現金に換算し「収入」欄(雑収入または事業収入)として計上。
- 経費:業務に直接使った費用(取材費、通信費など)を計上。
- 所得:収入 − 経費が20万円を超えると申告義務。
- 経費を差し引いた利益が20万円以下なら所得税は申告不要ですが、住民税申告は必要。
- 提出先・提出期限:翌年の3月15日(通常)。電子申告(e-Tax)を利用すると便利。
ギフトカード取得時の仕訳例は以下の通りです。
借方:現金(または受取報酬) 10,000円
貸方:雑収入 10,000円上記は国税庁認定の税理士からも推奨されている基本処理です (freee税理士検索)
副業アプリやポイントサイトでのケース
スマホアプリによる副業でギフトカード報酬を年間30万円分受け取り、経費5万円を計上した場合
- 利益:25万円 → 確定申告が必要。
- 経費が多ければ利益が20万円以下となり、申告不要となる場合もあり。
「月に数千円ずつギフトカードを受け取る」など、継続的な受け取りは事業所得と判断されるケースが多く、住民税・所得税ともに正式な処理が求められます。
| 項目 | 判断基準/内容 |
|---|---|
| 収入計上 | ギフトカードの額面を現金換算して収入計上 |
| 確認収入額 | 利益が20万円超の場合、確定申告が必要 |
| 経費計上 | 事業に関係する費用は必ず経費に |
| 住民税 | 所得が無くても収入があれば申告必要 |
| データ保存 | 明細・メール添付・領収書など保存 |
懸賞・キャンペーンでギフトカードを受け取ったときの一時所得

一時所得は、臨時的かつ不定期に得る所得を指します。懸賞金、競馬の払戻金、キャンペーン賞品などが該当し、以下の計算式で課税額が求められます。
課税対象額=(収入金額 – 必要経費 – 特別控除50万円)× 1/2
国税庁の所得税基本通達でも明確に定義されています。特に50万円特別控除がある点が大きな特徴です(国税庁|No.1490 一時所得) 。
特別控除50万円の意味と活用ポイント
- 年間の一時所得が50万円以下であれば、課税所得がゼロとなり、確定申告不要。
- 懸賞で10万円分のギフトカードを受け取れば、
- (100,000円 – 0 – 500,000円)× 1/2 = マイナス → 還ってくる税金はない状態。
次に、一時所得が50万円を超えた場合の課税イメージをご紹介します。懸賞で60万円分のギフトカードを受け取った場合を想定します。
- 計算:受領額 600,000円 – 特別控除 500,000円 = 100,000円
- 課税対象=100,000円 × 1/2 = 50,000円
この金額が他の所得(給与・事業等)と合算されて、所得税・住民税が計算されます。
もし抽選に参加する際の交通費や入力費用など実際に支出された費用があるなら、それも必要経費として控除できます。この場合、控除できる額が増える分、課税対象額は減少します。
- 事例A:SNS懸賞でAmazonギフト券10万円分当選
- 年間一時所得:–(10万円 – 50万円)× 1/2 = –20万円 → 課税対象ゼロ、申告不要。
- 事例B:自治体キャンペーンで60万円分の地域振興ギフトカード当選
- 課税対象:(60万円 – 50万円)× 1/2 = 5万円 → 他の収入と合算し確定申告が必要。
「一時所得の積み重ね」に注意
一時所得は年間の合算額で判断されます。複数の懸賞や抽選で受け取ったギフトカードを合計し、50万円を超える場合は合算した額での課税が求められます。
ギフト提供者がギフトカードを渡す場合の税務処理と注意点

家族や知人にギフトカードを贈るとき、 贈与に該当し、税務上は受け取る側に贈与税が課される可能性があります。
- 暦年贈与では年間110万円までは非課税ですが、それを超えると課税対象です(第2章参照)。
- 相続時精算課税制度を利用すれば、累計2,500万円まで非課税ですが、申告が伴い、相続時に精算されます(第2章参照)。
提供者自身には課税されませんが、受け取った人の税負担に関わります。
業務報酬や謝礼として渡す場合
企業や団体が業務の対価や謝意としてギフトカードを渡した場合、税務取扱いは「報酬」あるいは「料金」に該当します。
国税庁によると、報酬としての商品券・ギフトカード支給の場合、支払額が50万円を超えると源泉徴収が必要になります(所得税法第204条)。
50万円以下でも広告宣伝費などの名目によって源泉の要否が変わる場合があり、ケースごとの判断が必要です(No.2813 広告宣伝のための賞金等)(国税庁)
企業が社員や昨年の取引先などに謝礼としてギフトカードを渡す場合、「広告宣伝費」や「交際費」などで処理されます。ただし、勘定科目によっては源泉対象となるため、経理担当者は勘定科目の選定と源泉対応を慎重に行うことが求められます。
福利厚生費として渡す場合の給与課税回避条件
従業員への記念品や表彰用にギフトカードを渡すケースがありますが、これらが給与として課税対象にならないための基準もあります。
- 所得税基本通達では、記念品の支給が 社会通念上妥当で、1万円以下/5年以上の周期 に限られる場合、福利厚生費として非課税扱いできます (suzurankaikei.com)。
- それ以外では、給与等として所得税・住民税の課税対象となります。
源泉徴収の具体的要件と手続き
- 個人への謝礼、原稿料、講演料などの商品券・ギフトカード提供の場合、源泉徴収が必要です (suzurankaikei.com)
ギフト提供者が確認すべき要点チェックリスト
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的の明確化 | プライベートの贈与/業務謝礼/福利厚生かを整理 |
| 対象者の属性 | 家族・従業員・従業員以外などで税法扱いが異なる |
| 源泉徴収 | 支給額50万円超は必須、50万円以下でも目的次第 |
| 会計処理 | 勘定科目選定により源泉義務が変動 |
| 税務申告 | 経理部門や税理士へ計画的に相談・確認 |
✅ 本章まとめ
- 贈与目的のギフトは受贈者課税(贈与税)が基本
- 業務・謝礼目的で渡すケースは源泉徴収や所得税処理が必要、金額や勘定科目に注意
- 福利厚生品として渡すには、社会通念内・1万円以下・長周期の条件を満たす必要あり
- 50万円ラインが源泉徴収の一つの目安だが、目的や用途により変化する
デジタルギフトカードに関連する税法・通達の背景

所得税法では、金銭でなくても「無償または低価で提供される物や権利」は、経済的利益とみなされ課税の対象になります。これを現物給与として取り扱います(所得税法9条等) (「マネーフォワード クラウド」)。ここにデジタルギフトカードも含まれ、金銭に近い価値を持つものは課税対象となります。
社内レクリエーションでの景品と課税の判断基準
国税庁の「所得税基本通達36‑30」では、社内イベントなどのレクリエーション費用は所得課税しなくても差し支えないと明示されています。ただし、現金や金券(商品券・ギフトカード等)は除外対象とされます (濱田会計事務所)。ただし、この通達は「現物」のみを対象とし、現金や商品券、カタログギフトは対象外と明記されています。
したがって、デジタルギフトカードが自由に使える商品券として提供された場合は、非課税とはならず、給与所得または一時所得の対象になり得ることが重要です。
- 記念品は社会通念上相当である
- 処分見込価額が10,000円以下
- 永年勤続(10年以上)や創業記念など5年以上の周期で支給
福利厚生費としての取扱いと現金性の見極め
現金に類似する価値を持つギフトカードは、福利厚生費ではなく給与課税対象と認定される可能性があります (giftee for Business)
たとえば、用途限定(飲食専用)など換金性が低いギフトであれば福利厚生として認められるケースもありますが、自由に使えるギフトカード全般は課税対象になる点に注意が必要です。
税務処理の判断ポイントまとめ
| 判断ポイント | 非課税/課税 |
|---|---|
| レクリエーション景品 | 現金性あれば課税 |
| 永年勤続・創業記念品 | ・10,000円以下、・5年以上周期 → 非課税 ・現金・金券 → 課税 |
| 福利厚生使用(用途限定ギフト) | 換金性が低い→非課税の場合あり |
| 現物給与(自由選択可能) | 給与所得課税対象 |
デジタルギフトカードが「現物給与」とみなされる理由
- 金券と同様の用途自由性がある
- 使用制限が少なく、実質的な換金性が高い
- 社内外への配布で自由選択が可能な仕組みであれば給与とみなされる
このため、社内での記念日や表彰制度を理由にしても、社員が自由に選べる金券扱いのギフトカードは課税の対象となります。
デジタルギフトカードの税務取り扱い
デジタルギフトカードは同じ“ギフト券”でも、発行元・利用目的・提供者・受領方法によって税務上の扱いが微妙に異なります。
| ギフトカード種別 | 利用シーン | 税務上の扱い |
|---|---|---|
| (Amazon/Apple/Google) | 😊 ギフトとして受け取る(家族・友人・知人) | 贈与税の対象。年間110万円を超えると申告義務あり(第2章参照)。 |
| (Amazon/Apple/Google) | 👔 報酬として受け取る(副業・アフィリエイト等) | 所得扱い。利益20万円以上で確定申告が必要(第3章)。 |
| (Amazon/Apple/Google) | 🎉 懸賞・キャンペーンで受け取る | 一時所得。50万円控除後も課税対象なら申告が必要(第4章)。 |
| (Amazon/Apple/Google) | 🏢 企業から提供・支給(特典・福利厚生) | 賞金・景品・現物給与扱い。源泉徴収義務や経費処理(第5・6章参照)。 |
- 🎟️ 商品券・図書カード・QUOカードなど:現物として同等扱い。
使用用途や受け取り経路で贈与税・所得税・一時所得が課税される。 - 💳 プリペイド型クレジットカード:クレジット機能と異なり、贈与扱い・給与扱い・所得扱いなどケースによって税務対応が変わる。
ギフトカードを分割で複数回受け取る場合の税務リスクと対策

税務署は「1年間で110万円以内ならOK」と誤解している方に対し、「分割受け取りだから大丈夫」との誤認は通用しないと見ています。年度内に相当額を受け取っていれば、それが1回なのか複数回なのかは問題にならず、合算額で課税判断が行われます。
実際の調査では、分割や時期をずらして受け取った場合も累計でカウントされており、「不正節税」とみなされるケースがあります。分割受領の主な発覚ルートは以下の通りです。
- 受領記録の照合:Amazon、Google 等のプラットフォームには受け取り履歴が保存され、税務署が情報提供を受けるケースがあります。
- キャッシュフローの不整合:年末調整時コピーの銀行口座通帳などと照らされるなど、不自然な入出金パターンで調査対象に。
- 他の所得との関係性:年次申告書にギフト報酬や一時所得が記載されていない場合、不整合が察知されます。
分割対策としての保全策と明朗化
- 受領時のメールや明細を保管し、いつどの程度受け取ったかを明確にしておく
- Excel などで受領履歴を管理し、年間累計の集計資料を自己作成
- 必要に応じて税理士に相談
- 累計が高くなる見込みの場合、事前に暦年贈与として申告する
税法上、贈与・所得・一時所得では年度単位での合算判定がルールです。「分断して受け取った=合法」という考えは通用せず、過少申告や脱税とみなされることもあります。
| 項目 | 気をつけること | 対応策 |
|---|---|---|
| 分割で受け取る額 | 年間累計で判断され、課税要件を引き起こす | 年間の取得見込額を把握し、超過の可能性があれば早期申告 |
| 受領記録 | メールや明細を全て保存し、エビデンスを確保 | 明細をExcel等で整理しておく |
| 自己申告 | 未申告の場合でも、早めに更正申告を検討 | 税理士に相談し、過少申告加算税の回避を検討 |
| 調査対応 | 調査対象となる可能性あり | 資料整理をあらかじめ準備、調査に備える |
税務署による調査や取り締まりの事例と対応戦略

近年、SNSインフルエンサーや副業が普及する中で、DMや報酬でギフトカードを受け取るケースが増加しています。特に以下のようなケースが「調査対象」となる可能性があります。
- 定期的・継続的にギフトカードを受領している
- 抽選や懸賞ではなく、明らかに「収益目的」で受領されたもの
- 明細情報が曖昧で、収入の記録が整備されていない
追徴課税や重加算税の例
- 📌 ケースA:副業バイラル動画配信者のアフィリエイト報酬
ギフトカード報酬を年間200万円受賞し、無申告だったため税務調査に。
→ 所得税+加算税で約50万円の追徴課税に発展。
→ 調査時に提示した「DMとメールの保存」が救いとなり、3年遡っての修正申告で追徴を抑制。 - 📌 ケースB:懸賞景品として複数枚ギフト券を受領
懸賞で合計70万円分のギフトカードを受領したが申告せず。一時所得となり3%の重加算税課税。
→ 一時所得の100万円控除を利用せず所得計上された状態が問題視。
税務署が使用する情報収集方法
以下の手段によって、税務署は受給データを収集し、申告漏れを発見しています。
- アフィリエイトASPの支払調書情報提供制度
- SNSプラットフォーム上の配信記録監視
- デジタルギフト券発行会社からの資料提供要請
- 口座取引記録との突合
税務署の取り締まり傾向と対応ポイント
| 調査対象ヒント | 税務署の対応 | 自衛策 |
|---|---|---|
| SNSで頻繁に報酬を発表 | 調査リストに追加 | 投稿数・報酬額データを保存 |
| 懸賞や抽選で高額ギフトを受領 | 一時所得と判断される | 懸賞履歴と明細を保管 |
| 定期収入でギフトカード受領 | 事業所得とみなされる | 経費・領収書類も整理 |
調査通知が届いたらどうすべきか?対応マニュアル

- 受領記録や応募履歴を整理し、事実関係を明らかにする
- 必要に応じて税理士に早期相談し、修正申告や軽減交渉を依頼
- 書類提出の範囲と回答期限を正確に把握
- 調査官との面談対応では、正直かつ冷静に説明することが重要
追徴課税・重加算税について
- 過少申告加算税:無申告または誤申告の場合、10〜15%のペナルティ。
- 重加算税:仮装・隠蔽が明らか場合、35〜40%の重税負担となるリスク。
調査時の修正申告や自主申告により、この負担を軽減することが可能です。
✅ 本章まとめ
- デジタルギフトカードは、SNSや副業と併せて税務署の調査対象リスト入りしやすい
- 過去の未申告や誤申告が判明すると、追徴課税・重加算税のリスクが高まる
- 調査通知が届いた場合は、記録整理・修正申告・税理士相談が重要
- 日常的な記録保存と年末の収支確認で、調査対応力や安心感が大幅に高まります
他の国におけるデジタルギフトカードの税制度比較 🌍
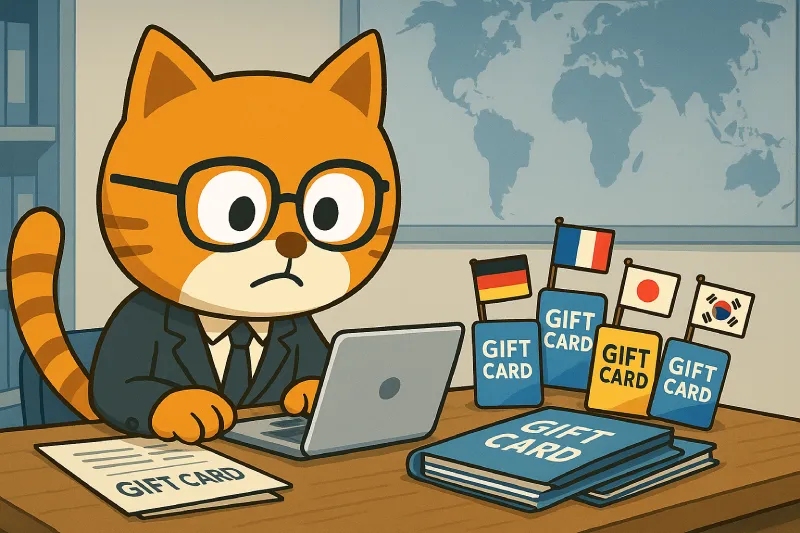
日本在住でも海外発行カードを受け取ったり、居住先が海外だったりするケースもあり得ます。本章では、主としてアメリカとイギリスの税制を、日本の制度と比較しながら解説します。なお、各国の非課税枠は年度ごとに変更されます。
| 項目 | 日本 | アメリカ | イギリス |
|---|---|---|---|
| 贈与税非課税枠 | 110万円/年 | 19,000ドル/年 | 3,000ポンド/年 |
| 所得区分 | 所得税・一時所得 | Ordinary Income | Income Tax / Benefit-in-Kind |
| 源泉徴収要否 | 高額・用途による | Form 1099-NEC/-MISC | P11D報告義務 |
| 一時所得扱い | (収入-50万円)×½ | Prize Income源泉あり | 懸賞金など源泉あり |
| 制度透明度 | 税務署裁量あり | 法律で指定 | 法律・申告制度あり |
海外からカードを受け取るときの注意点
- 為替レートの確定方法
為替差益により日本での課税が変動するケースもあるため、受取日の為替で換算が一般的です。 - 二重課税防止協定の確認
アメリカ・イギリスとの協定により、現地で源泉徴収されたものが日本でも同額控除できる場合があります。 - 報酬受給者の居住者区分
海外在住者でも日本の税法上「居住者」と見なされる場合、全世界所得課税対象になる。
デジタルギフトカードに関する税金対策と専門家相談ガイド 🧭
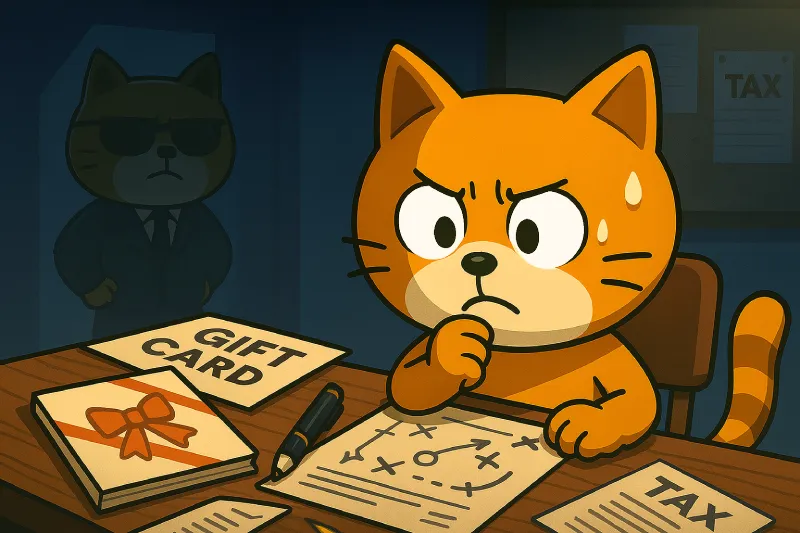
デジタルギフトカードによる収受は税務上のリスクが高いです。そのため、納税リスクを最小化し、安心して活用できる方法をご紹介します。
節税対策の基本方針
- 贈与として贈る・もらう場合
→ 年間110万円の非課税枠を意識。超過する可能性があれば相続時精算課税制度の活用を検討。 - 報酬として受け取る場合
→ ギフトカードも「収入」として計上し、20万円ラインを超えれば確定申告+住民税申告。 - 懸賞・キャンペーン当選品
→ 年間50万円超になると課税対象。複数当選の可能性を考慮し、事前に集計・試算を。 - 企業から配布する場合
→ 慶弔以外のギフトカードは「現物給与」扱い。福利厚生・交際費として計上する場合も含めて用途を明確化。
個人事業主・法人のための節税ヒント
A. ギフトカード購入時の経費計上のコツ
金券ショップでの購入:購入額ではなく「額面、実使用額」で課税判断される可能性があります。節税が目的と判断されると指摘対象に (税理士・社労士・行政書士|税理士法人松本)。
経費として計上するなら、「購入時ではなく使用時」で処理するのが原則。
使用目的・使用先・受領者など具体的に、会計帳簿や帳面に記録を残す。
B. ギフトカード支給時の税務処理(法人の場合)
慶弔目的以外で大量に支給する場合、交際費として会計処理するのが原則ですが、帳簿に明確な目的・対象を記録しておく( 北千住税理士事務所)。
税理士に相談すべきケース:見極めポイント一覧
| 場面 | 相談が有効な理由 |
|---|---|
| 年間収受額が非課税枠に近い/超過しうる場合 | 相続時精算制度や暦年贈与を組み合わせた対策が可能 |
| 副業報酬にギフトカードを継続して受ける場合 | 事業所得化して経費計上の幅を広げる戦略がとれる |
| 懸賞やキャンペーン当選が複数あり、年間で50万円超 | 一時所得の記載方法・控除の適用判断など専門家判断が必要 |
| 法人で従業員に記念品として複数配布する場合 | 福利厚生費・現物給与区分の適用要件を満たしているか判別が重要 |
| 海外発行ギフトカードや外国居住の関係者がいる場合 | 二重課税、為替計算、外国人贈与制度の扱いを見誤らないため |
よくある質問(FAQ)
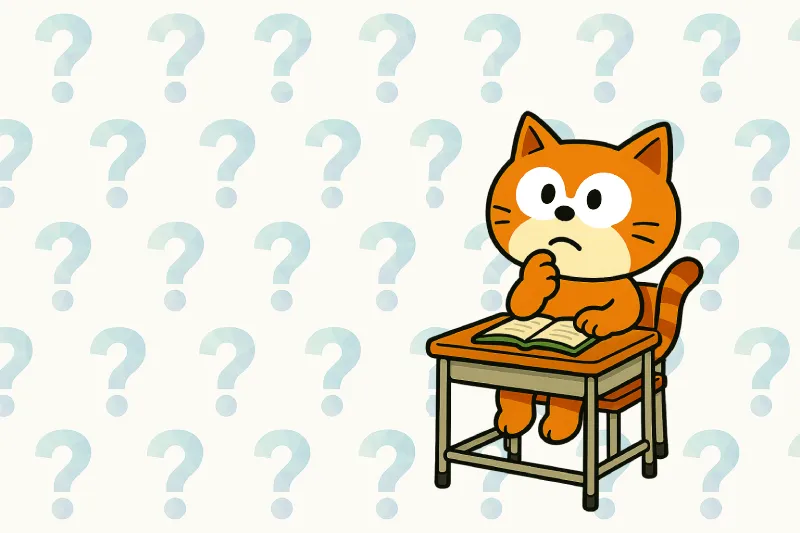
贈与された相手が税金を負担するものであり、贈った側からは課税されません。ただし贈与税課税対象額になる金額を渡す場合、「相続時精算課税制度」の選択などにより、適切な手続きが必要です(第2章参照)。
課税対象所得=19万円 − 1万円 = 18万円 → 20万円未満のため、所得税の確定申告は不要です。ただし住民税申告は収入ありとして対応が必要です(第3章参照)。
日本居住者が受け取る場合、所得区分(贈与税・所得税・一時所得)に応じ、日本円換算して課税されます。為替レートや二重課税回避協定の確認が必要です(第10章参照)。
いいえ、税法では年度ごとの累計で判断されます。分割だとしても110万円を超える場合は贈与税の対象となります(第8章参照)。
・受領履歴や情報を整理し、事実関係を明らかにする
・必要に応じて税理士に相談し対応
・自主的に修正申告を行い、ペナルティ軽減を図る
・調査官には誠実かつ冷静に説明する
📌 参考リンク集
- 国税庁(贈与税):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/zoyo/
- 国税庁(所得税通達):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591.htm
- 国税庁(懸賞等の一時所得):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
- SmartCareer(報酬としてのAmazonギフトカードの課税):https://www.smartcareer.net/amazon-gift-card-and-tax-rule/
- GIFTEE(福利厚生ギフトカードの税務取扱い):https://giftee.biz/columns/welfare-expense-tax/
- Manegy(贈与税・暦年課税の解説):https://www.manegy.com/news/detail/8325/
免責事項
本記事は、2025年7月時点の公的情報・信頼性のある税務解説に基づいて作成されていますが、正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。税制は年度や政府方針により変更されることがあり、また個別の事例によって税務判断が異なる場合もあります。
特に贈与税・所得税・一時所得の適用区分、申告要否、控除の可否、調査対象の判定などは、実際の取り扱いが税務署の判断や納税者の状況により変わることがあります。本記事の内容をもとに税務申告・判断・対応をされる場合は、必ず税理士などの専門家にご相談ください。
本記事で紹介したリンク先や出典情報は、それぞれの運営者の責任において提供されているものであり、当サイトはその内容について一切の責任を負いかねます。読者様の税務判断・手続きにより発生するいかなる損害についても、当サイト運営者は責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。




